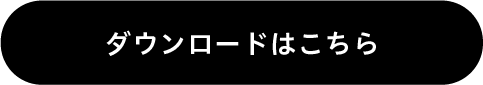TAKIブログ
テーマ:デザイン
更新日:2025.03.28
デジタル庁と現役デザイナーが考える、新たな時代に求められるデザイナー像。
ブログ編集部

こんにちは、ブログ編集部です。先日、株式会社Too、公益社団法人 日本広告制作協会主催のセミナーが開催され、弊社執行役員でクリエイティブディレクターの藤井賢二が、デジタル庁で広報、デザインを所管しブランド戦略策定に取り組んでいる外山雅暁氏との対談を行いました。今回は前半にセミナーレポート、後半に対談の様子をお届けします。

デジタル庁ってどんなところ?
デジタル庁は2021年に誕生した新しい省庁。「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を」をミッションとし、国のデジタル化推進における中心的な存在です。
デジタル庁企画官である外山氏はこのミッションに、より具体性を持って取り組んでいると言います。
外山 「私たちはデジタル化を進めていますが、それそのものを目的としているわけではありません。デジタル化が果たされることで、一人ひとりのニーズにあったサービスを提供できるようになり、日本人全員が幸せを感じられる社会になる。これこそがデジタル庁の最終目標です。」
デジタル庁は、一般的な行政官である国家公務員はもちろん、都道府県も含む地方公務員、さらに民間企業出身の非常勤公務員など、さまざまな背景・境遇を持ったメンバーで構成されているのが特徴です。働き方についてもかなりフレキシブルで、オフィスに出社して働くメンバーもいれば、静岡や軽井沢、神戸など、地方在住でリモートワークで働くメンバーも。新しい省庁だからこそ、新たな働き方や価値観を積極的に取り込みながら運営されています。
また、省庁は一般的に縦割りの組織構造ですが、デジタル庁は横軸の組織も並行して存在しているのが特徴です。縦割りのグループに対して、デザイナーをはじめとする民間の人材がフレキシブルに関わることで、多様な視点からの議論を推進しています。
デジタル庁にはマーケティングの部署も存在しており、デジタルデータを元にしたサイト改善にも取り組んでいます。どのようなユーザーがどのようにサイトを利用しているのか、データからニーズを推測し、ユーザー目線に立った改善を目指しています。
デジタル庁のこれまでの実績
設立間もない庁ですが、その実績は非常に豊富です。例えば、コロナ禍にリリースした『接触証明書アプリ』。通常は外部と協力するケースも多いのですが、緊急性が高い案件だったため、そのほとんどをデジタル庁の職員が内製しました。
他にも、マイナンバーカードの申請数や保険証との紐づけ数をインフォグラフィックで視覚化する『政策データダッシュボード』もリリースされています。マイナンバーカードの申請数などは元となる数字が大きいため、単に数字だけ伝えられても状況をイメージしにくいものですが、それを見える化することで、よりリアルな指針を描けるようになりました。またユーザー側へのサービスとして、『マイナポータル』もリリースしています。
また最近では、事業のデジタル化を目指す自治体や民間の利用者向けにHP制作などのデザインが必要になるシーンで活用できる『ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック』をリリース。そのまま使えるデザインの定義やパーツが盛りだくさんの『デザインシステム』なども提供しています。
外山「一見ちゃんとできているサイトであっても、視覚障害のある人には使いづらいなどといったアクセシビリティの課題は多いです。政府のサイトはアクセシビリティの要件が決まっており、その要件をクリアしたうえで公開しているのですが、担当者に知見がなく機械的にチェックすることが多いため、実際には使いづらい状態であることも多々あります。それを解消するためには、誰もが使えるデザインパーツを提供するのが早いだろうと考え、デザインシステムをリリースしました」
このようにデジタル庁では、他の省庁や自治体、民間企業もデザインやUI・UXを活用できる基盤整備を推進しています。
行政におけるデザインは、「政策デザイン」「行政のデザイン」「顧客が触れるモノのデザイン」の3つに大きく分けられます。政策と行政サービスに関しては行政人材が強く、サービスとモノのデザインは民間人材が強い傾向があり、それぞれの専門分野や得意分野でスキルを発揮し、より良い行政のサービスデザインを目指しています。
サービスデザインとは、顧客体験のみならず、顧客体験を継続的に実現するための組織と仕組みをデザインすることで新たな価値を創出するための⽅法論のこと。わかりやすく言えば、商品やサービスそのものだけでなく、購入前に触れる広告や販売時の接客や対応、さらにアフターサービスに至るまで、そのすべてをデザインしていこうという考え方です。
では、行政においてサービスデザインがなぜ重要になるのでしょうか。外山氏はこう語ります。
外山「私たちがデザインしリリースする各種サービスやツールは、行政と国民の接点となるものです。元々行政と国民が直接的に触れるシーンというのは決して多くはありませんので、その数少ない接点が『見にくい』『使いにくい』という印象になってしまうと、行政そのものへの不信感へと繋がってしまうこともあるかもしれません。行政のデザインは、国民からの信頼を得るための窓口としても機能させないといけないのです」
デジタル庁と現役デザイナーが考える、これからのデザイナー像
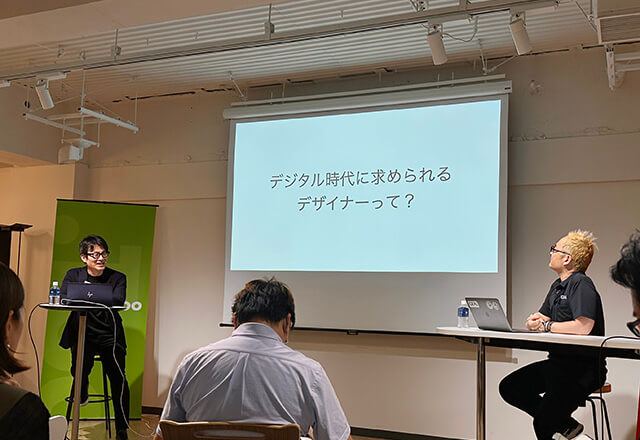
講演後半には、外山氏と弊社藤井によるフリートークがありました。
藤井「デジタル庁で働くのは魅力的ですね。どんなことができるデザイナーが向いていますか?」
外山「活躍しているのはコミュニケーション能力が高く、物事を進める力を持ったデザイナーが多いですね。外部の人と協力体制を作ったり、他部署と関わったりと、仕事上デザイナーだけで動くことはほぼありません。デザインのプロセスにある、共感したり観察したりといったことと近しいですが、意見を引き出したり方向性を決めたりできる人が向いていると思います」
藤井「なるほど。行政は基本的に失敗が許されない環境ですよね。しかし、その中でデザイン庁はPDCAを回しながら作って壊して試して、というデザインを推進されているのがすごいですね」
外山「民間と行政の人間が半々の比率で、多様な人材が集まっているからこそ、こういった文化が生まれたのだと思います。この文化を体験した行政官が異動すると、異動先の省庁の文化も変わり、将来的には霞が関全体に変化が訪れそうです。一方で、評価制度に課題が残ると感じています。例えばサイトを新しく作るという職務を与えられた場合、リリースできたら評価的にはOKとなります。その先でどう使われるかまでは評価されないため、フォローに時間を割きづらいんです」
藤井「それは私もよく分かります。かつての広告デザインは、作って発表して終わりという感じがありました。しかし今は、リリースした後のお客様の反応を見て、テストを重ね、どんどん改善していくことが重要になっています。これからのデザイナーには、作って終わりではなく、さらに成長させられるという感覚が必要になるでしょうね。外山さんは、デジタル時代に求められるデザイナー像はどのようにお考えですか?」
外山「デジタルは皆にとって使いやすいことが必須です。ですので、アクセシビリティやUI・UXをよく理解していて、使いやすいモノを作るデザイナーが現代は評価されます。しかし、AIで様々なUIのパターンを出せるようになりましたし、使いやすいサイト構成の方向性はいずれ集約されていくでしょう。それに、人間は面白くないと嫌になってしまいます。皆が使いやすいだけのサイトばかりでなく、新たな創造性も求められるはずです。ですので、人間にしかできない創造性を付与できる人材がさらに求められていくようになると考えています」
藤井「確かに。例えば結婚式の二次会といったような場面で、新しい技術を積極的に活用して楽しいことをやりたがるような人が向いていそうです。スマホでくじ引きしたり、二次会の様子をデジタルアーカイブに残したり、色々な角度で考えられます。皆を盛り上げるために、色んなツールを楽しみながら取り入れられる人は、きっとデザイナーとしても将来性があるのでしょうね」
デジタルの力で新しい時代に突入しつつある省庁の世界。デジタル庁のさまざまな政策や取組によりデジタル化が進み、日本はもっと便利になっていくことでしょう。これからの時代に求められるデザイナーの姿をはじめ、多くの示唆に富んだセミナーでした。
■外山雅暁 氏
デジタル庁 企画官(前 特許庁 デザイン経営プロジェクト/審判官)
金沢美術工芸大学美術工芸研究科(修士課程)修了。アーティスト活動を経て、2001年に特許庁入庁。意匠審査官、総務部国際課、留学等を経て、2012年から経済産業省商務情報政策局クリエイティブ産業課にてデザイン政策とクールジャパンを担当し、デザイン思考の研究会の立上げ等を行う。その後特許庁でデザイン経営宣言の策定に従事すると共に、デザイン経営プロジェクトの立ち上げを担当。現在デジタル庁にて、コミュニケーションデザインチーム(デザイン・広報・報道等)を管理し、デジタル庁のブランド戦略策定に取り組んでいる。
■藤井賢二 氏
株式会社たきコーポレーション 取締役/デザイナー/クリエイティブディレクター
広告のデザイン、クリエイティブディレクションはもとより、近年はデザインマネジメントを支援する デザインコンサルティングとして、企業へUXデザインを提供。また、デザイン思考とシステム思考による社会課題に寄り添うプロダクトデザインを多数発表している。また、図画工作科を中心としたアート教育についても活動するなど、デザインの幅を広げている。